ハイキャリアの転職に特化したコンサルタントが、最適なポストを提案します
仕事のやりがいは何ですか?
今の仕事で満足な点と変えたい点はありますか?
あなたにとってのワークライフバランスとは?
パソナキャリアはあなたのキャリアを相談できるパートナーです。キャリアカウンセリングを通じてご経験・ご希望に応じた最適な求人情報をご案内します。
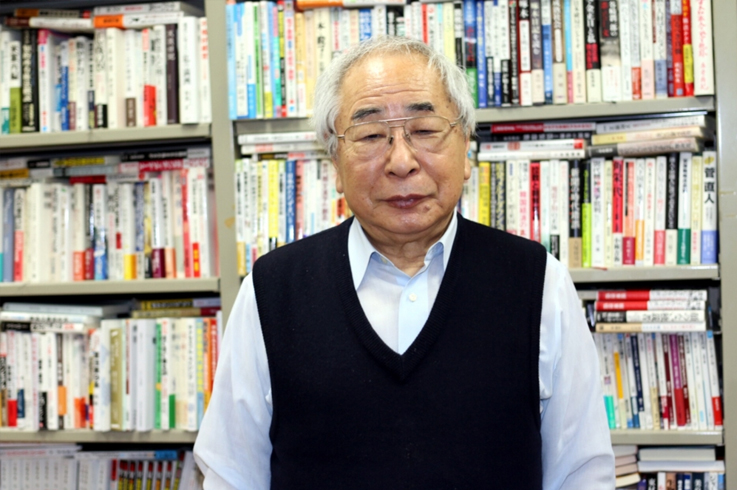
人生の先輩たちに、失敗の経験とそこからのリカバリー方法について聞く当連載。今回は元フライデー編集長・伊藤寿男さんに、「あの事件」の話題を振り返りながらお話を伺います。
『フライデー』という写真週刊誌がある。講談社発行のこの雑誌は、2015年度に年間26万部を売り上げるなど、出版不況といわれるなかでも好調を維持している。だが、最盛期には毎号200万部もの売上を記録していた。
個人情報に関して今よりも規制が緩やかで、スクープにタブーが少なかった当時、芸能から政治までカバーできる精鋭を40名ほど集めた編集部は、向かう所敵なしの勢いだった。しかし、その牙城が大きく揺らぐ事件が起こった。「フライデー襲撃事件」だ。
当時の取締役第一編集局長(『フライデー』創刊編集長)伊藤寿男さんにお聞きするのは「怒られても前向きでいる方法」。他にも幾多の訴訟を起こされてきたという伊藤さんは、どのようにピンチを乗り越え、立ち直ってきたのだろうか。
編集長は、雑誌の質とともに部数を上げるのが仕事です。ただ、私は46歳で講談社の役員になったもので、社内には「若造が役職について」と、快く思わない人が多かったようです。私は都会の出身ではなく、静岡の小倅なので「負けすか!!(静岡の方言で「負けるか!」の意)」といつも思っていました。
いろいろな事件の当事者になった私のことを指して、周囲の人間は「伊藤はもうダメだ」と思っていたかもしれません。でも、自分では挫折を感じたことは一度もありませんでした。例えば、いわゆるフライデー襲撃事件の後、講談社を退社して、学研と共同で新しい週刊誌を創刊しました。その雑誌は2年で廃刊になってしまったのですが、それでも「1つ失敗をした」くらいの感覚でしたね。
当時はフライデーがあまりにも売れていたから、編集部におごりがありました。その点で行きすぎた取材があったことは、反省すべきところです。襲撃のきっかけになった12月8日の取材以前にも、記者がたけしさんを徹底的にマークして取材を続けていた時期だったので、お互いにわだかまりがあったんです。
たけし軍団のプライバシーに踏み込んだ記事、他にも社会的タブーに関する記事を掲載することで、圧倒的なアンチを生むと同時に、週刊誌の地位を確立させたという自負はあります。
たけしさんが逮捕された後、釈放される時には講談社前にある警察署に、彼の支援者や野次馬が300人も集まりました。三島由紀夫の自決を取り上げた創刊号の時も、たくさんの野次馬が会社の周りを取り囲んでいましたね。
フライデー襲撃事件当時は、編集部員たちを守らなければならないと思っていたので、気に病んでいる暇はありませんでした。早朝の3時に編集部に襲撃があって、4時には自宅で休んでいた私のもとに電話がかかってきました。ただ、第一報を聞いたときには「これで講談社を辞めなければいけないな」と思いました。立場上、社長など自分の上に立つ人はいましたが、その人たちに責任を取らせる訳にはいかない。自分のところで食い止めるには、私の辞職が必要だったので。
事業にはいつだって大変な局面があるものです。そのくらいは、挫折とは思わない。常に「明けない夜はない」「冬来たりなば春遠からじ」と自分に言い聞かせていました。乗り超えられない壁なんて、存在しないんです。そういえばその頃、日経ビジネス誌から、「敗者の弁」に寄稿してほしいという依頼を受けたことがありました。「自分が敗者だとは思っていないから、受け付けない」とお断りしましたけどね(笑)。
スクープの数も雑誌の中で一番でしたし、冊数が売れていたのでその分訴訟は多かったですね。当時は講談社の中だけでなく、週刊誌全体でも一番の金額を請求されていたのではないでしょうか。今では一件の訴訟で億になるようなものもありますから、総額では及ばないとは思いますが。とはいえ、しっかり裏を取って記事にした上での訴訟ですから、訴えられるのも仕事のうちでしたね。
訴訟をする側も、訴えたという事実が大切なので、実際には10あるうちの8件は取り下げられていました。そして裁判で負けても、事実はあるのに立証できなかったということがほとんどです。
昨今は名誉毀損の問題が厳しくなっているから、週刊誌はやりづらくなっているでしょうね。プライバシーについては、フライデー事件の前と後でガラリと様相が変わってしまいました。あの事件をきっかけに、週刊誌が個人的な領域に踏み込まなくなり、それに合わせて売り上げも激減していったと考えています。
「身に余ることはしない」ということでしょうか。高い下駄を履けば、転ばせようと狙う人が必ずいます。だから、背伸びはしないことにしています。私はギャンブルも、煙草も、お酒も、ゴルフもしません。フライデーを週刊で出し続けることがそもそも一番のギャンブルだったから、それ以上の刺激は必要なかった。
芥川賞や直木賞作家、政治家が一時の気の迷いで舞い上がり、数年で潰れていく姿を嫌というほど見てきました。反対に司馬遼太郎さんや松本清張さん、実績があるのにおごらない偉大な財界の人たちの背中を見ては、「勘違いして、のぼせたらいけない」と自分を戒めていましたね。
会社の中だけではなく、高校や大学の先生、先輩でもいいので、何でも話せる年上の知り合いに、1人か2人はいつでも連絡がつくようにしておくといいでしょう。後は会社内で着実に実績を上げておくこと。業界で「あいつはやるな」という噂が広がれば、怒られたときにかばってもらえたり、仕事が続いたりして有利になります。ただぼんやり待っていても、成功はやってきません。自分の足で歩いて、天に見られているという恐れを持ちながら、着実に進んでいくのがいいと思います。
(小松田久美+ノオト)
伊藤寿男さん
1934年生まれ。昭和33年に講談社に入社。『現代』編集長、学芸図書第二出版部長、『週刊現代』編集長を経て、取締役第一編集局長を歴任し『フライデー』編集長を兼務。現在、月刊テーミス編集主幹。

「シンクタンク」とは?意味や仕事内容、転職方法をプロが解説

あなたは面接でどう見られている? 7秒で選ばれ、30秒でアピールできるイメージ戦略を考えよう

「自分の能力、その全てを振り絞って挑戦するから面白い」45年間まだ見ぬ財宝を探す、トレジャーハンター・八重野充弘さん|クレイジーワーカーの世界

元・引きこもりが「逆就活サイト」で就職、そしてヤフーに転職するまで

徒弟制度に憧れ帰化。筋肉と庭園を愛する庭師、村雨辰剛さん |クレイジーワーカーの世界

このくしゃみ、花粉症と思ったら「生物アレルゲン」が原因だった!? 専門家に聞いた、オフィスや家での対策法
年収800万円以上、年収アップ率61.7%
仕事のやりがいは何ですか?
今の仕事で満足な点と変えたい点はありますか?
あなたにとってのワークライフバランスとは?
パソナキャリアはあなたのキャリアを相談できるパートナーです。キャリアカウンセリングを通じてご経験・ご希望に応じた最適な求人情報をご案内します。