ハイキャリアの転職に特化したコンサルタントが、最適なポストを提案します
仕事のやりがいは何ですか?
今の仕事で満足な点と変えたい点はありますか?
あなたにとってのワークライフバランスとは?
パソナキャリアはあなたのキャリアを相談できるパートナーです。キャリアカウンセリングを通じてご経験・ご希望に応じた最適な求人情報をご案内します。
<目次>

「仕事の幅を広げたい」「会社の将来性に不安を感じる」「年収や待遇面をアップしたい」。転職を望む人たちに複数回答で理由を訊くと、この3点が目立ちます。中でも年収をきっかけに検討し始める人は業界や年代に関わらず、4~5割にのぼり、転職を考える際の大事な視点と言えるでしょう。
厚生労働省の「雇用動向調査」(2022年)によると、転職後の賃金が「増加」した人の割合は34.6%、「減少」が35.2%、「変わらない」が29.0%。転職者全体で見た場合、上がる人、下がる人、変わらない人が、いずれも3割前後という結果になっています。
このデータをもう少し深掘りして見てみると、「増加」と「減少」それぞれの割合は、「1割以上」と「1割未満」にわけて数値が出されています。それによると、全体のうち、賃金が「1割以上増加した人の割合」は23.7%、同じく「1割以下減少した人の割合」は26.3%でした。
つまり、「転職したことで、賃金が減少したという人は3人に1人くらいいて、さらにその中でも1割以上減った人は4人に1人前後だった」ということがわかります。この数字は定年退職年齢世代の数字が大きく影響していますが、少なからず年収が下がってしまう人がいるということも事実です。
国税庁の「民間給与実態統計調査」によると、企業で働く人の2021年の年間平均給与は443万円(正社員・職員508万円)でした。この数字には毎月の給料や手当、賞与(ボーナス)が含まれます。
前段で説明した1割以上の増減したケースで考えると、正社員をベースにした場合、年収の1割にあたるのは50.8万円となります。単純に12か月で割った場合、月額約4万2千円の減少になります。
のちほど改めて説明しますが、働く人のライフステージや住環境などにより、「どれぐらい年収が下がっても許容できるか」は異なります。
ライフイベントの重なる30代~40代で、年間50万、月間4.2万円の年収減少は、キャリアアップや雇用不安が転職理由の人でも捨て置けない数値ではないでしょうか。
先の表を、年代別に見てみると、20~54歳までの転職者で、賃金が「増加」した人の割合は3~4割台となっています。逆に「減少」は2~3割台です。この世代に限っていえば、全体の傾向として、転職で賃金が減るよりも、増えるか変わらない人が多いと言えます。
ただ、55歳を過ぎると厳しくなるのもまた現実のようです。55~59歳で「増加」と答えた人の割合は20.5%、60~64歳ではわずか13.1%にとどまりました。一方で、「減少」との回答は、55~59歳で48.8%、60~64歳では66.5%に上ります。
年収が下がる影響は、日々の暮らしに直結します。
価値観や生活様式の多様化で、一律に年代でライフステージを語ることが難しい時代ではありますが、最大公約数的に、20代、30代、40代における「転職で年収が下がる影響」について考えてみましょう。
大学進学率は長期的に上昇傾向にあり、今では男女とも5割以上が大学に進みます。また2~3割の子どもたちは専修学校に進学します。日本企業にはまだ新卒一括採用の慣行が残っていることを考えると、働く20代の多くは社会人経験が比較的浅いと言えるでしょう。即戦力としてではなく、将来性を考えたポテンシャル採用として期待されることが多く、待遇面で見たこの世代の特徴は、転職して年収が増える割合が多いことです。
前述している、厚生労働省の「雇用動向調査」(2022年)によると、転職者に占める賃金が増えた人の割合は、20~24歳で47.1%。25~29歳でも42.9%を占めます。もちろん、減った人もそれぞれ24.6%、30.8%いますが、「下がったとしても再チャレンジしやすい年代」とは言えそうです。
ただ、年齢や社歴、役職などに応じて給与が決まる企業も少なくないのが現状。また、短い期間で転職を繰り返している転職者の採用に難しい企業も多いため、現在の会社でキャリアを積み上げていくか、賃金が増える可能性の高い20代のうちに転職するかは、将来的な展望も含めて、よく吟味し判断するのがいいでしょう。

30代は結婚や出産などライフステージに変化が起こりやすい時期です。厚生労働省の「人口動態統計」(2020年)などによると、平均初婚年齢は夫31.0歳、妻29.4歳。第1子出産時の母親の平均年齢は30.7歳です。いずれも中央値で見ると、もう少し若くなります。

また、国土交通省の「住宅市場動向調査」(2021年)によると、注文住宅や分譲マンションなどの世帯主のうち、最多を占めるのは30代となっています。
これらを重ね合わせると、20代後半から30代にかけて結婚や出産を経験し、30代でマイホームを手に入れる人が相対的に多いということがわかります。

子どもを授かった夫婦の場合、結婚や出産、子育ての費用が生じる一方、育休や産休などで一時的に世帯収入がダウンする事態が起こりえます。日々の生活費の平均は3人家族で約30万。また、住宅ローンなどの固定費を抱え始める時期でもあります。
ライフステージが変わり、自分だけではなく家族も含めた暮らしを考えなければならないことの多い30代。とりわけ年収が下がる可能性のある転職は、家族ともじっくり相談の上、慎重に判断するのがベターと言えます。

結婚し、子どもを持つ選択をした夫婦では、40代で子育てについての出費が増えます。内閣府の調査(2009年)によると、食費や子どもの預貯金・保険なども含めた1人あたりの年間子育て費用は、小学生で約115万3000円、中学生では約155万6000円でした。産まれてから22歳で大学を卒業するまでの子育て費用の総額について、すべて国公立でも2500万円以上、私立だと4000万円を超えるとの民間試算もあります。
夫婦ともに30歳で子どもを授かったとすれば、40代の10年間は子どもの中高時代と重なります。大学に進学する場合、受験期も40代の終わりから50代の初めにかけてです。子育て費用がもっともかさむのが40代と言えるでしょう。 国税庁の「民間給与実態統計調査」(2021年)によると、40~44歳の平均年収は485万円(男509万9000円、女326万2000円)、45~49歳では510万8000円(男637万5000円、女332万2000円)。仮に共働きでも、子どもが私立に通ったり、第2子、第3子を設けたりすれば、暮らしは楽ではありません。 転職しても、賃金が増える人の割合が多い40代。子育てにはお金がかかりますが、幼い頃と比べれば、先行きの見通しはつきやすくなるはずです。子育て費用や家族の生活費、老後の貯え、現在の会社での昇給・昇格の見通しなどを総合的に勘案し、転職の是非を判断するといいでしょう。
全体で見た場合、転職で賃金が増える人は3割強。減る人もほぼ同じ割合です。年代については先ほど触れましたが、それ以外に減少する要因として考えられるのは何でしょう?

日本の雇用慣行は変わりつつあるとされますが、まだ新卒一括採用を行っている企業が大半を占めます。日本経済団体連合会(経団連)のアンケート(2021年)によると、「新卒一括採用を実施している」と答えた企業の割合は91%となっています。ただ、この数値は5年程度先には79%にまで下がるとも予想されています。
一方で、大手を中心に今後増えると見込まれているのが既卒者の「ジョブ型採用」。特定の職務を担うスキルや実務経験のある人材を採用する方式です。
経団連のアンケートによると、企業はほかに、新卒者・既卒者の「職種別・コース別採用」も増やすとしており、今後、専門的な知識やスキル、経験を備えた即戦力、技術革新や新しいビジネスモデルに対応できるリスキリング(新しい知識やスキルを学びに身につけること)がますます求められるようになりそうです。
こうした傾向が強まる中、新しい会社ですぐにいかせる専門性や技能、経験を身につけて行かないと、結果として、年収低下につながる恐れがあります。
上京し、就職した都会を離れ、生まれ故郷で仕事を探す「Uターン転職」。都会で生まれ育ち、就職したあと、地方に移って仕事を見つける「Iターン転職」。地方から都会に出て働いたのち、ふるさととは異なる地方で職を得る「Jターン転職」。
IT機器の発達などで、地方でも都会に近い働き方ができるようになりました。少子高齢化により人口が減り続ける地方にも、これらの転職を後押しする動きがあります。
自然豊かで人のつながりが濃い地方都市で暮らすのは、都会とはまた違った良さがあるでしょう。都会より物価が安いことも大きな利点の一つです。
その半面、地方では給与水準が低い傾向にあるのもまた事実。これを端的に表すのが法律で定められた最低賃金の格差です。
最低賃金は、地域の物価を加味するなどして都道府県ごとに決められます。近年、全国的に上昇傾向にあり、2022年の改定では31円引き上げられ、全国加重平均額で961円になりました。ただ、1000円を超えているのは東京都、神奈川県、大阪府の3都府県のみ。平均額を下回る地域もたくさんあります。
都会から地方への転職を検討する際、こうした点もよく踏まえ、年収が下がる可能性も視野に入れておくことが必要でしょう。

大企業と比べ、中小規模の企業では賃金が低い傾向にあります。厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると、2022年6月に企業が支払った所定内給与額の平均(男女計)は、大企業34万8300円、中企業30万3000円、小企業28万4500円でした。管理職、経営クラスになる50代以上ともなると大企業と小企業では10万円以上の開きがあります。
ただ、今は中小規模でも、市場規模の拡大が予測される業界など、成長が著しく、今後、賃金の上昇が見込まれる企業もあります。その逆に、業績の頭打ちに苦しんでいる大企業も存在します。転職先を探す際、現時点での企業規模だけでなく、業績の見通しや従業員数の推移なども確認しておく必要があります。
給与は「基本給」と「手当」に大別されます。基本給は年齢や社歴、職務内容などによって、手当は役職や勤務地、残業時間などによって、一人ひとり細かく計算されています。基本給は残業代やボーナス、退職金の算出基準としても用いられます。
また、給与のうち基本給と手当が占める割合も、企業ごとに違います。
基本給を低めにし、社員のやる気を引き出すために、実績と手当を強く連動させている企業もあれば、チームワークや年功序列を重んじて、手当であまり差がつかないように基本給を厚めにしている企業もあります。一長一短があり、絶対の正解は存在しません。
現在の勤め先と転職希望の企業を「もらえるお金」で比べる場合、手当の種類や額、基本給と手当の比率、ボーナスや退職金への影響にも注意して下さい。一見、「転職したら年収が下がる/上がる」と感じられても、実際には正しくないかもしれません。

転職により年収は上がることも下がることもあり得ます。下がる可能性が高い場合、それでも踏み切るべきか、見送るべきか。判断の参考になりそうなポイントをまとめました。
「人事給与制度の違い」のところで説明したように、給与は主に「基本給」と「手当」に分けられます。基本給が低くても手当が厚い企業や、その反対の企業もあります。まずは転職を希望する企業の制度をよく確認してください。年次昇給の仕組みがある企業では、転職初年度のみ賃金が下がるケースもあります。 当座の年収増減だけではなく、少し長いスパンで考えることが大切です。
その後年次昇給があれば現在の年収に戻るまではどのくらいの期間か、自身のライフプランと突き合わせたうえで、自分が求めるキャリアが手に入るのであれば、進めていくことも良い判断かと思います。
現職より大幅に年収ダウンすることが見込まれる場合、内定をもらったから、就きたい職業だったから、だけでははく、生活していけるかを考える必要はもちろんあります。
また希望した企業から内定を得たものの、グローバル化し、環境が激変しやすい市場では、業績が急速に悪化し、先行きが不透明になってしまったというようなことも、実際に起こりえます。海外での想定外の紛争や自然災害、株価や為替の変動なども、企業業績に大きな影を落とす要素です。
こうした事態に転職を強行するのは得策ではないでしょう。業績不振が長引けば、期待通りの年収を得られなくなる可能性もあります。その企業や業界を取り巻く環境が、どのように推移するか見極めるため、内定を辞退するのも選択肢のひとつです。
再就職先の賃金が転職前より低い場合、国の「就業促進定着手当」を受け取れる可能性があります。これは雇用保険の被保険者に対し、早期の再就職と再就職先での定着を促す目的で設けられたもので、受け取るには以下の条件を満たす必要があります。
支給額は「(離職前の賃金日額-再就職後6か月間の賃金の1日分の額)×再就職後6か月間の賃金の支払い基礎となった日数」で算出。離職時の年齢によって上限額が設けられています。
再就職から6か月が過ぎた日の翌日から2か月の間に、ハローワークへの申請が必要です。条件を満たす可能性があるならば、ぜひハローワークに相談して下さい。
冒頭、転職を希望する理由として、年収や待遇以外に「仕事の幅を広げたい」と答える人が多いと説明しました。「現状では経験やスキルを十分にいかせない」「イノベーティブ/クリエイティブな業務ができない」「年功序列で年長者の意見ばかりが通ってしまう」といった悩みを抱え、自らの成長やキャリア形成に不安を感じていることの裏返しだと思われます。
また、社風や職場の雰囲気になじめなかったり、残業や休日出勤が多すぎたりして、心身に不調をきたしている人もいるでしょう。
新卒から定年までは一般的に40年前後。人生の多くを占める「働く時間」を、やりがいを感じられずに過ごすのは、決して幸せなことではありません。
やりたい仕事や積み重ねたいキャリアが明確だったり、健康を損ねるほどの職場環境だったりするのなら、たとえ年収が下がったとしても、転職へ一歩踏み出す勇気を持つことが大切です。「自分にとっての優先順位は何か」をよく考え、転職活動に臨んで下さい。

年齢やスキル、企業の所在地や規模などにより、年収が下がりやすい転職があることを解説してきました。年収以外のバリューを求めた転職も、もちろん尊重されるべきです。とはいえ、もし自分の努力や外部の力を借りることで、年収低下を避けることができるのであれば、やってみる価値はありそうです。
専門的な知識やスキル、経験を備えた即戦力を求める企業が増えつつあるのは、先に述べた通りです。身についた技能などをいかせそうな転職先を探すのが、最も理にかなったやり方です。
一方で、未経験の異業種を目指す場合はどうすべきでしょうか。
一つのヒントになりそうなのが、新卒時の就職活動です。
ほとんどの学生には特別な経験もスキルもありません。それでも採否が分かれるのは、採用側がその人材の「資質」の有無をはかったからです。
前出の経団連のアンケートでは、大卒者に特に期待する資質として、約8割の企業が「主体性」と「チームワーク・リーダーシップ・協調性」を挙げています。自ら考え、行動し、輪を乱さずに率先する――。こうした資質は、努力次第でどの職場でも育むことができます。そうして築き上げた資質を、新しい職場でどう生かすのか、これまでの経験や知見をどういう形で生かせるのか、を考える必要があります。
転職先の人事給与制度をよく確認することの大切さは、これまで述べた通りです。それだけにとどまらず、転職希望先や業界の研究も欠かせません。企業の求人要項を熟読し、公式サイトやプレスリリース、企業SNSなどをチェックしましょう。また、新聞や業界誌、会社四季報などからは、その業界の賃金相場や取り巻く環境をうかがい知ることができます。求められる人材像や業界動向を熟知している転職エージェントも力強い味方になるはずです。転職は情報戦。あらゆる手段を用いて、入念に情報を集めて下さい。
年収を下げない転職を目指すのであれば、年収交渉は不可欠です。提示された金額が自分のスキルや実績と見合わないと感じたままで転職すると、入社後のパフォーマンスやモチベーションに影響しかねません。
交渉のタイミングは、採用面接時であれば、面接者から年収の希望を尋ねられたり、「最後に何か訊きたいことはありますか?」と逆質問を求められたりしたときなどに確認するとスムーズです。 内定後、給与や福利厚生などを調整する目的で行われる「オファー面談」で交渉するのも一案です。 選ばれる側として、年収交渉にためらいを感じる人もいるかもしれませんが、提示された金額に納得ができないのであれば、思い切って交渉をしてみることも大切です。 ただし、「金銭面だけ考えている」と捉えられたら悪印象となってしまうので、希望を伝える際には明確な理由を添え、また、現在の年収や、業種職種の年収相場からかけ離れていないことが必要です。
転職エージェント経由での転職活動の場合、キャリアアドバイザーが本人に代わって希望の年収を交渉することも可能です。
年収をアップすることができれば、転職活動は成功したと言えるかもしれません。
ですが、年収や報酬は、企業の業績や業界トレンドによって影響も受けますし、業務量が増えたり、重い責任を負う必要が出てきたりということもあります。
大切なのは、自身のキャリアをどう考えているか。そのキャリアのために必要な転職になっているかどうか、モチベーションを維持できる年収や評価を得られるかどうかです。自分が転職してよかった、ここでがんばろうと思える仕事に出会うことこそが転職成功と言えるのではないでしょうか?
転職エージェントはキャリアアドバイザーが、求職者の希望を聞き、また企業側のニーズも把握した上で、求人と求職者のベストマッチを目指して支援します。
転職を検討されているなら、ぜひ転職エージェントを活用した転職も、検討してみてください。

転職エージェントの視点から、転職活動の始め方、自己PRの作り方、面接対策や円満退職の秘訣まで、転職ノウハウをわかりやすくコラムでご紹介します。
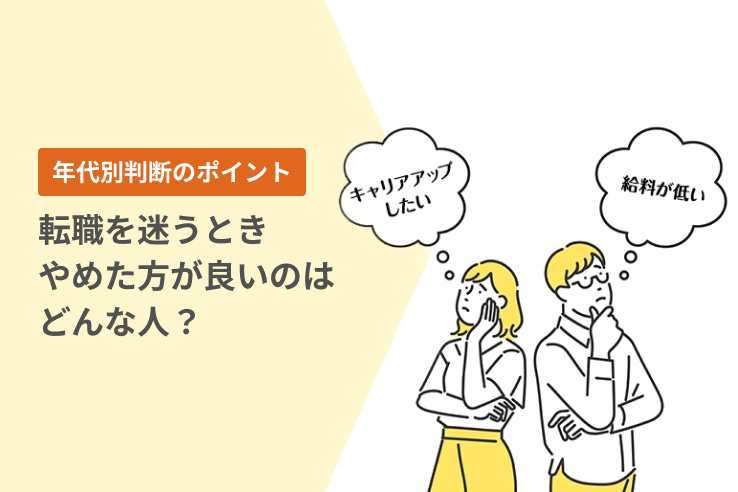
転職を迷うときやめた方が良いのはどんな人?年代別判断のポイント

同業他社へ転職してもいい?競業避止義務や転職成功のポイントを解説
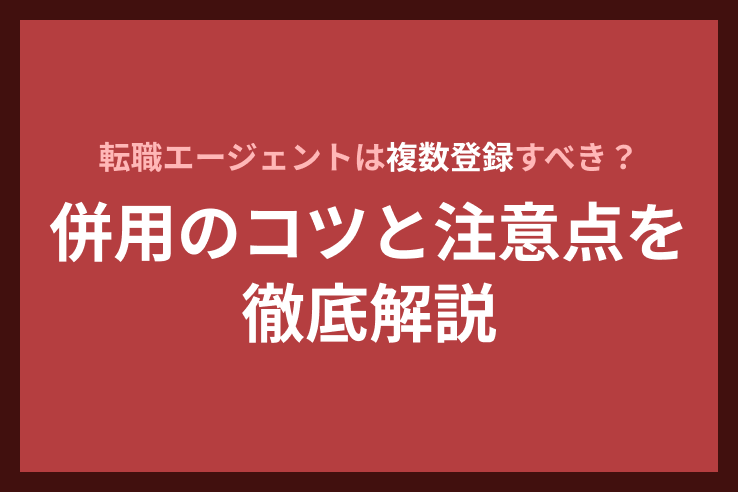
転職エージェントは複数登録すべき?併用のコツと注意点を徹底解説

転職におすすめの時期は?ベストなタイミングと成功のポイント
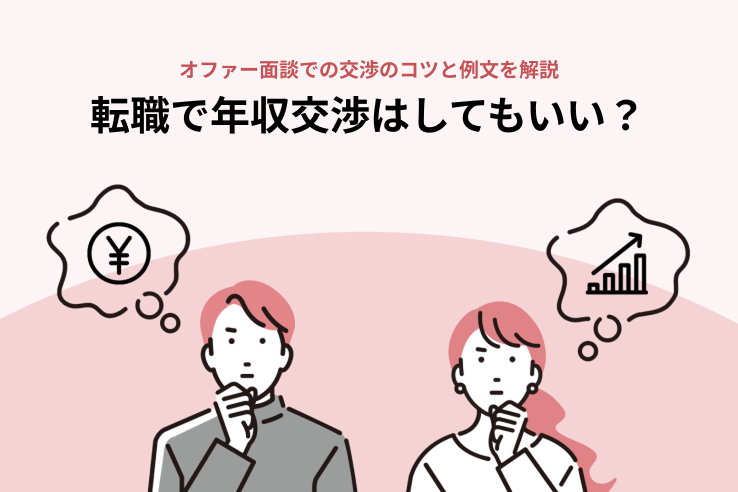
転職で年収交渉はしてもいい?オファー面談での交渉のコツと例文を解説

転職が「怖い」「不安」と感じる原因と解消法
年収800万円以上、年収アップ率61.7%
仕事のやりがいは何ですか?
今の仕事で満足な点と変えたい点はありますか?
あなたにとってのワークライフバランスとは?
パソナキャリアはあなたのキャリアを相談できるパートナーです。キャリアカウンセリングを通じてご経験・ご希望に応じた最適な求人情報をご案内します。