ハイキャリアの転職に特化したコンサルタントが、最適なポストを提案します
仕事のやりがいは何ですか?
今の仕事で満足な点と変えたい点はありますか?
あなたにとってのワークライフバランスとは?
パソナキャリアはあなたのキャリアを相談できるパートナーです。キャリアカウンセリングを通じてご経験・ご希望に応じた最適な求人情報をご案内します。

離職してからの転職活動は、採用する企業にとってもマイナスな印象を与えるケースがあり、7割以上の方は現職中から転職活動を開始します。しかし、仕事が忙しすぎて転職活動の時間が取れなかったり、職場に隠しながら仕事と転職活動の両立をしていたりすると、ばれないようにすることが難しく心が折れてしまったり、転職を諦めてしまったりして後悔することになりかねません。そのため、やむを得ず転職活動を本格的に始めるのは、今の会社を退職してからにしようと考えている人もいるでしょう。 しかし、退職後の転職活動は、資金面での不安があります。そこで、退職してから転職活動をしたいと悩んでいる方に役立つのが雇用保険です。 今回は、雇用保険の基礎知識から受給資格、雇用保険の種類についてご紹介します。
<目次>
働く人の生活を守り、失業者の再就職を支援する制度として、雇用保険制度があります。一般的に「失業保険」や「失業手当」と呼ばれる給付も、雇用保険の1つです。
雇用保険は、国が管理・運営する公的な保険制度です。従業員の雇用安定や失業時の再就職支援、再雇用の促進などを目的としています。 保険料は、事業主と労働者でそれぞれ負担する仕組みとなっています。保険料率は毎年見直されており、厚生労働省の発表によると令和4年度の雇用保険料率は、一般の事業で労働者が賃金総額の0.3%、事業主が0.65%を負担すると定められています。農林水産業など一部例外はありますが、原則、1名以上の労働者を雇っている企業は、雇用保険への加入を義務づけられています。
雇用保険を受給するためには、一定の要件を満たす必要があります。雇用保険の中でも一般的な「基本手当」の受給資格について見ておきましょう。 基本手当は以前、「失業保険」や「失業手当」などと呼ばれていたため、今でも雇用保険の中でよく知られている手当です。会社を辞めた離職者の再就職先探しを支援する手当として支給されています。
雇用保険を受給するためには、被保険者期間を満たしている必要があります。 例えば、仕事のミスマッチや人間関係、家庭の事情などで会社を辞めた場合は「自己都合退職」扱いとなります。自己都合退職の場合、離職日以前の2年間で、通算12カ月以上の被保険者期間があることが、雇用保険の受給条件です。 一方、勤めていた会社の倒産・解雇など、やむを得ない事情で退職を余儀なくされた場合は「会社都合退職」扱いとなります。会社都合退職は、離職日以前の1年間で通算6カ月以上の被保険者期間があることが受給条件となり、「特定受給資格者」と呼ばれます。
つまり、自己都合退職の場合は1年以上、会社都合退職の場合でも半年以上の被保険者期間がなければ給付は受けられないということです。ただし、同じ会社で一定期間加入している必要はなく、過去に転職経験がある場合でも、異なる会社の合計被保険者期間が条件を満たしていれば、受給対象となります。
雇用保険の受給要件を満たしていれば、基本手当が支給されます。基本手当の給付日数や受給金額の条件について、参考にしてください。
雇用保険の給付日数は、90日から最大360日で、給付日数の期間には個人差があります。給付日数は被保険者期間のほか、失業理由や年齢、就職困難者であるかどうかなどの基準から判断されます。 例えば、会社都合の退職者は、自己都合の退職者に比べて給付日数が長くなる傾向があります。会社都合退職の場合、再就職の準備をする時間的な余裕がないまま離職を余儀なくされたと考慮されるため、給付日数が長くなります。
基本手当日額とは、1日あたりに給付される基本手当の金額で、離職直前の6カ月間で支払われた賃金に基づいて算出されます。基本手当日額の上限は年齢ごとに定められており、令和4年8月1日時点で29歳以下は6,835円まで、30歳~44歳は7,595円までとされています。下限額は、年齢を問わず1日あたり2,125円です。
雇用保険には基本手当以外にも、労働者の生活と雇用を安定させるための手当があります。その中から、利用者が多い手当や給付についてご紹介します。
失業者の再就職を支援するための手当で、主なものに次の2つがあります。
基本手当の受給資格者を対象とした雇用保険です。離職後、早い時期に再就職先が決まった場合、基本手当の支給日数が残っていることがあります。基本手当の支給日数が3分の1以上残っている早期の再就職者は、再就職手当を受給することができます。
再就職手当の受給者が再就職先で6カ月以上雇用されており、かつ前職よりも賃金が一定の割合で低い場合は、就業促進定着手当の受給対象となります。ただし、基本手当の残りの支給日数の40%が上限です。
基本手当の受給資格者であっても、離職後に自身で手続きを行わなければ給付は受けられません。基本手当を受給する際の注意点について見ておきましょう。
退職後は、前職の会社から交付された離職票を住民票がある地域のハローワークに提出し、求職の申し込みを行います。離職票のほかに、マイナンバーの確認書類、身分証などの証明書、写真、印鑑、預金通帳等の書類が必要です。 離職票提出・求職申し込みを行ってから7日間を「待機期間」と呼びます。この期間は基本手当が支給されないため注意しましょう。
手続きを終えた後は、指定の日時で行われる受給説明会へ参加する必要があります。その後は1回目の「失業認定日」までに最低2回以上の求職活動を行い、その内容を「失業認定申告書」に記入し、ハローワークに提出します。
基本手当を申請できる期間は、離職した翌日から1年間です。受給申請期間を過ぎてしまうと、基本手当の受給資格を喪失することになるため、離職後は速やかに手続きを行いましょう。 万が一、会社から離職票が送られてこない場合は早めに連絡する必要があります。
受給資格を満たしていれば基本手当を受け取ることができますが、手続きから受給までには「給付制限期間」があります。 例えば、退職の理由が自己都合などの場合、7日間の待機期間の後、さらに3カ月の給付制限期間があります。つまり、ハローワークで手続きを行った日から3カ月以上、基本手当を受給できない期間があるのです。
基本手当は、申請後すぐに支給されるわけではありません。資金不足にならないよう、計画的な転職活動を行いましょう。
失業してから再就職までの生活を保障してくれる雇用保険は、働く人にとって心強い制度です。雇用保険の受給資格があれば、転職先を決めないまま会社を辞めざるを得ない状況になっても、給付を受けながら再就職先を探すことができます。 しかし、自己都合による退職により数カ月以上の離職期間が発生した場合、必ず面接時にも理由を確認され、ネガティブな理由による転職活動なのではと計画性を疑われる可能性があります。転職を考えている人は、「給付が受けられるから大丈夫」と安易に退職するのではなく、転職先が決まってから退職するか、あらかじめ貯金をしておくなど、離職後に困らないように余裕を持った転職の計画を立てましょう。
(この記事の情報は令和4年8月時点のものです)
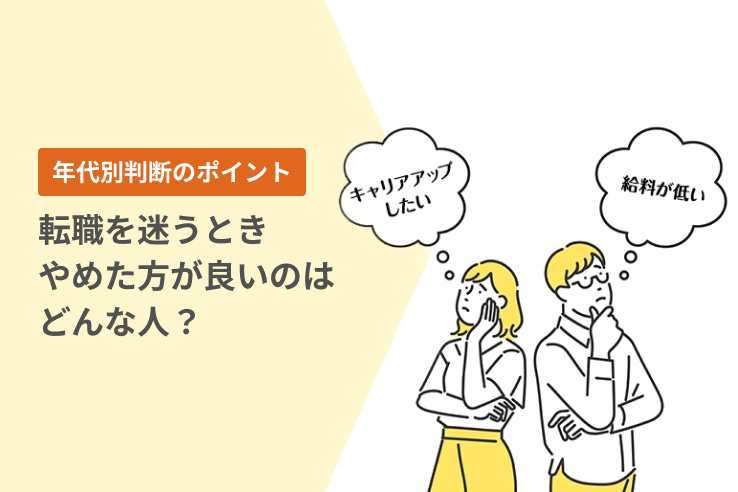
転職を迷うときやめた方が良いのはどんな人?年代別判断のポイント

同業他社へ転職してもいい?競業避止義務や転職成功のポイントを解説
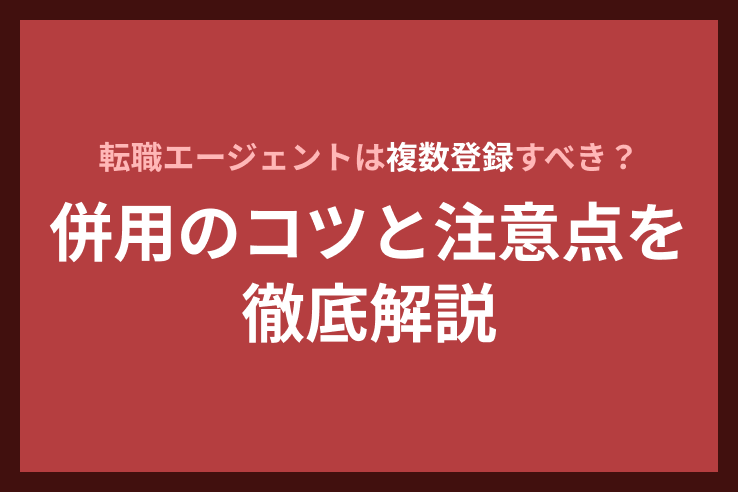
転職エージェントは複数登録すべき?併用のコツと注意点を徹底解説

転職におすすめの時期は?ベストなタイミングと成功のポイント
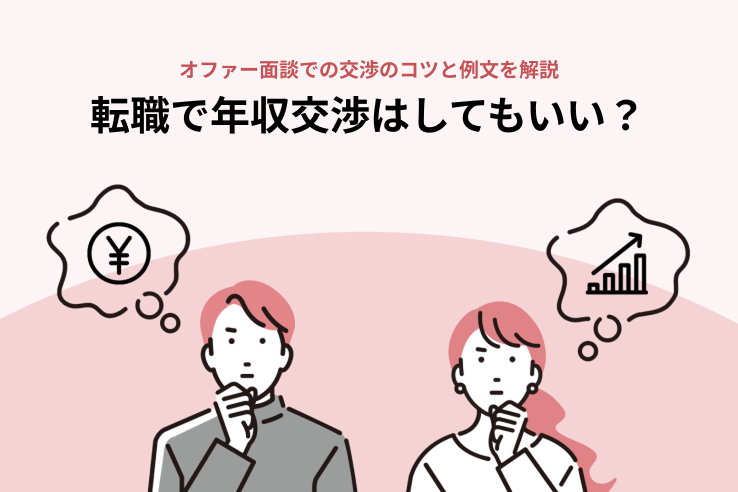
転職で年収交渉はしてもいい?オファー面談での交渉のコツと例文を解説

転職が「怖い」「不安」と感じる原因と解消法
年収800万円以上、年収アップ率61.7%
仕事のやりがいは何ですか?
今の仕事で満足な点と変えたい点はありますか?
あなたにとってのワークライフバランスとは?
パソナキャリアはあなたのキャリアを相談できるパートナーです。キャリアカウンセリングを通じてご経験・ご希望に応じた最適な求人情報をご案内します。