ハイキャリアの転職に特化したコンサルタントが、最適なポストを提案します
仕事のやりがいは何ですか?
今の仕事で満足な点と変えたい点はありますか?
あなたにとってのワークライフバランスとは?
パソナキャリアはあなたのキャリアを相談できるパートナーです。キャリアカウンセリングを通じてご経験・ご希望に応じた最適な求人情報をご案内します。
「社内横断の技術組織を終わらせました」
こんな告白エントリーに見覚えのある方もいるのではないでしょうか。
このエントリーの主は、サイバーエージェント子会社のCyberZ所属で、国内No.1スマホマーケティングツール「F.O.X」サービスマネージャーの門田矩明さんです。
門田さんは、2017年の1月にこのようなエントリーも書いています。
残念ながらこの技術組織は3カ月ほどで解散してしまいますが、その後に書いた「記録」としてのエントリーが多くの人の心に響き、広がっていきました。しかし、この後どうなったのかについては、あまり語られていないように感じられます。
そこで、今回は門田さんへ「横断組織が終わった後」について、お話しいただきました。
インタビューの中で見えてきたのは、自身の経験を踏まえたうえで門田さんなりに考えた「横断組織論」、そして前々から考えていたという「市場において無価値にならないエンジニア像」でした。エンジニアとして自分がいまひとつ伸び悩んでいると感じている方、自分に合うチームを探している方、そしてエンジニアの採用や育成、マネジメントに関わっている方、必見の内容です。
──エンジニアの知人に「社内横断の技術組織を終わらせました」エントリーについて聞いてみたら、やはり知っている人が多かったです。あの記事の「その後」が気になっている人も多いと思いますが……
門田さん(以下、門田) 結構バズリましたよね。あの記事は土日でバズっていて、週明け月曜日にビビりながら出社しましたが、静かなもんでした……。みんな気を使ってくれていたのかなと思います(笑)
今はもともといた事業部に戻っています。全社で何かをやるというのは一回忘れて、自分の事業部でやりたかったことをやり直すことにシフトしています。
―先日開催されたイベントでもお話しされていましたが、現在はVP of Engineeringのような立ち位置で組織課題を解決されているそうですね。この考えは以前からお持ちだったんですか?
門田 いや、前からあったわけではなく、たまたまきっかけがあったんです。僕が横断組織を立ち上げる前は、CTOのような具体的に技術を使う立場だったんですが、横断組織をやっていた時期にしばらくそこから離れていて。僕が組織課題にコミットしている間に、今まで僕がやっていたようなことは他のメンバーがやってくれていました。戻ってきたところでせっかく上手く回り始めた状態を無理にもとに戻すのも変な話だなと思い、僕は人的なことも含めた「組織的な課題」にフォーカスして解決していこうとしたんです。
―技術の知識があるエンジニアが組織課題を解決する、という考え方は最近提唱され始めたのでしょうか?
門田 そうですね。一番センセーショナルだったのはメルカリの「CTOとVP of Engineeringをわけます」という宣言でした。「エンジニア組織の課題解決はCTOがしなくてもいい」というのが、僕からするととてもわかりやすかったです。この宣言が出るまでは、エンジニアに関することは全部CTOがやらないといけないと考えていました。周りのエンジニアからよく聞くのは、CTOになると組織課題ばかり増えて、技術にどんどん疎くなっていくという話です。「うちのCTOは何もわかっていない」、「クラウドとか触ってないのに偉そうなこと言うな」とか、どこに行っても聞くので……。CTOの役割は肥大化していたと思います。そこを分けても良いんだ、という気付きは大きかったですね。
―横断組織を立ち上げるべきか否かは、どのように見極めるべきだとお考えですか?
門田 事業の性質に左右されると思います。CyberZには全部で3つの事業があり、スマートフォン広告代理事業と、OPENREC.tvというゲーム実況やプレイ動画配信メディアを展開するスマートフォンメディア事業、F.O.Xのアドテクノロジー事業に分かれています。OPENRECはtoCですが、僕らが作っているF.O.XはtoBで、ビジネスモデルとしてはまったく別です。技術的にカブる部分は少ないものの、それぞれ独立しているので、技術課題の解決に横断組織が有効かと思ってやってみたら、エントリーで書いたとおり有効ではなかった感じです。
僕は昔、サイバーエージェントのAmebaで似たような横断組織に携わっていて、その時の成功体験があったからCyberZでも横断組織に挑戦しました。ただ僕がいた頃のAmebaは、toCのメディア事業が中心の組織で、当時はスマホアプリごとにチームがあり、みんな技術スタックが似ていたんですね。なので、横断組織が有効でした。これがメディア事業とゲーム事業を横断するものを作ろうとすると、問題に突き当たっていたんだろうなと思います。
―実際に立ち上げて、解散し、もとの組織に戻って意識は変わりましたか?
門田 最初に抱いていた課題について、CyberZでは「横断組織が解決策ではなかった」という答えが出ました。となると、課題は各事業部の中で解決していかなければならないので、自分がやるべきことの絞り込みができたのです。
例えば技術広報も、横断組織を立ち上げたときは「会社全体のブランドがない」ことを課題に思っていました。クックパッドみたいな状態を目指して技術ブランディングを始めたんですけど、会社のブランドイメージだけではエンジニアは入社しないという課題が逆にはっきり見えてきたんです。エンジニアとして働くことをイメージする際、「会社」の中で働くというよりは「プロダクトチーム」の中で働くというイメージの方が実際に近いですよね。同じように「気に入った会社に入る」というよりも、「気に入ったプロダクトのチームに入る」のが正しい形だと気が付きました。そのため、ブランディングも個別のプロダクト主体に切り替えています。
―切り替えてから、何か変化はありましたか?
門田 ありましたね。3年前からプログラミング言語Scalaのカンファレンス(ScalaMatsuri)にCyberZとしてスポンサードしていたのですが、それによって求職者や業界の方から、CyberZは全プロダクトにScalaを使っているイメージがついていました。実際にフタを開けるとF.O.Xでしか使っておらず、毎回説明に困っていて。勘違いから入ると、訂正するコストが高いんですよね。
今年からは試しに「F.O.X」としてスポンサードすることに切り替えてみたのですが、そうすることで「F.O.XがScalaを使っているんですね」とミスマッチがなくなったんです。これを機に採用もプロダクトごとの見せ方に軌道修正しました。CyberZへの入り口がプロダクトになったことで、ちゃんとプロダクトに興味がある方に来てもらえるようになり、かなり効果が出ていると感じています。
―これからのエンジニアに対して、「こう育ってほしい」という考えはありますか?
門田 やはりフルスタックエンジニアの市場価値が高まっています。WEBサービスを作っているエンジニアに対してはtoB、toC問わずこの傾向ですね。昔はインフラレイヤーが巨大化していて、専門知識がかなり必要でした。今はパブリッククラウドにシフトしてきているので、どちらかといえばソフトウェアを作る延長線上の感覚に近いですね。昔はゴリゴリ書いていたプッシュ通知機能も、今はクラウドで用意されているサービスを使えば書かなくて済みます。なので、技術領域が増えれば増えるほど、もっと別の部分にクリエイティブな時間を費やせると思います。その上で新サービス、新しいビジネスをつくる意識をもってほしいなと思います。
―エンジニア発信でビジネスを作っていくということですね。
門田 エンジニアの方には、「こういった機能を作ったほうがいい」という意見はどんどん言ってほしいです。「これだったら自分で全部作れる」と言えると、なお良いです。「自分からサービスを良くしよう」というひとつの意識をもってもらいたいです。「俺はエンジニアだから技術以外は知らない」といった意識で言われたものをつくっているだけでは、価値がなくなってしまうと僕は思っています。窓口業務がBOTやAIに置き換えられてしまうように、似たようなことがエンジニアリングでも起きるのではないでしょうか。
―門田さんは社内エンジニアの方と毎月1対1で面談をしているとお伺いしましたが、面談でもそういった話をされているのでしょうか?
門田 そうですね。目先の評価(価値)ではなくて、中長期的な個々人の市場価値についての話をしたりします。フルスタックの話や、ビジネス方面へのチャレンジなどはこの面談で話をすることが多いです。
CyberZはエンジニアだけやりたいという人は少なくて、「なんでそれを作るの?」と理由を気にする人が多いと感じています。F.O.Xもそうですが、CyberZは今ないものを作る仕事が多いので、正解がないんですよね。本当に必要かどうかをみんなで議論して、必要ならどうしたらお客さんが使ってくれるか、市場で一番良いものになるか、を思考する必要があります。正解がないのは苦しいですが、主体性を持って取り組むと楽しさが変わってきますよ。
―いろいろなところからアイディアが生まれて楽しそうですね。
門田 そうですね。もちろんお客様や市場が何を求めているかをヒアリングや調査をして突き止める「マーケットイン」も重要なので、「僕らが考える最強の機能」を考える「プロダクトアウト」の両方が出来ている状態が大事だと思います。
―門田さん自身は今後、どのようなキャリアや目標を描いていますか?
門田 F.O.Xを大きくするのが今の目標です。日本でのシェアでいうと、AppStoreの売上トップ200のうちの35%のアプリに導入していただいており、シェアはNo.1の状態ですが、グローバルのシェアはまだこれからという状況です。Facebookやtwitter、Googleなど、グローバルの大きなメディアとのインテグレーションは既にできているので、グローバル展開の時期に入りました。既に中国、韓国、台湾などのエリアでは、成果が出始めています。日本という難しい市場でNo.1であるという実績を武器に、グローバルでもNo.1をとる。これが今のわかりやすい目標です。
さらに先の展望もあります。F.O.Xでお預かりしているデータをお客様向けに使うことを前提として、スマホや広告、アプリという枠にこだわらず、お客様が思いついていない活用方法を提案していきたいです。お客様が新しいビジネスをF.O.Xを基軸にして出来るようにしていこうと思っています。
* * *
失敗を教訓にし、新たな自分のやるべきことを見つけ取り組んでいる門田さん。社内エンジニアとの面談では、「今やっていないことをやればいい」とアドバイスしているそうです。横断組織を立ち上げてみたり、ブランディングの方針を変えてみたりと、「今までにやっていないことをやる」姿勢を体現している門田さんがF.O.Xの未来を語る様子は、とても生き生きとしていました。身近な課題をひとつずつ解決することが、自分のキャリアを切り拓いていく一番の近道なのかもしれませんね。
「Force Operation X(F.O.X)」は、2011年2月に国内で初めてスマホアプリ向け広告効果計測を実現させたスマホアプリ向け広告効果計測ツールです。
Facebook社の「Facebook Marketing Partners」や、Twitter社「Twitter Official Partners for MACT」、Google社「App Attribution Partner」、LINE社「Ads Measurement Partner」に公式パートナー認定されており、累計6,500超のアプリに導入されています(2018年1月現在)。日本国内のアプリマーケットにおける導入シェアは国内No.1。グローバルにおいてもアメリカ,韓国,中国,ヨーロッパ等で提供を開始し、インタビュー内でも述べられているように、今後はグローバルでの展開に注力していくフェーズとなっています。
(執筆者:佐野創太)
* * *
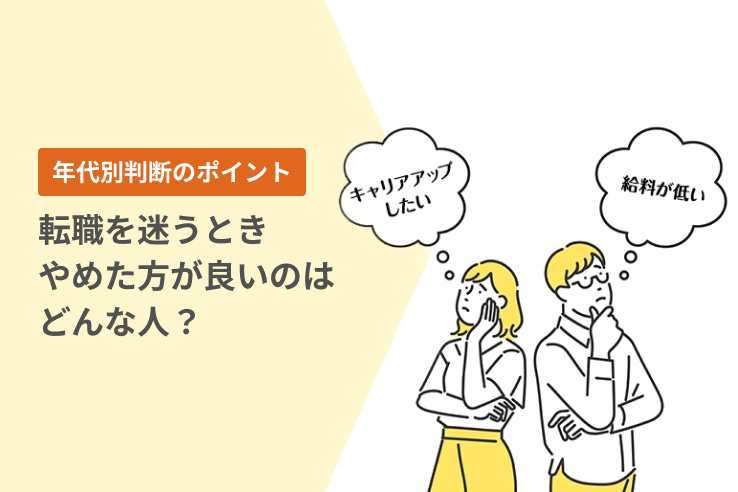
転職を迷うときやめた方が良いのはどんな人?年代別判断のポイント

同業他社へ転職してもいい?競業避止義務や転職成功のポイントを解説
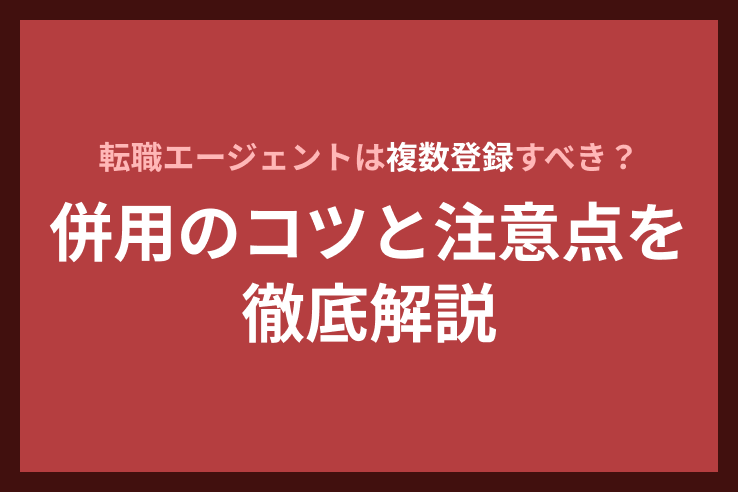
転職エージェントは複数登録すべき?併用のコツと注意点を徹底解説

転職におすすめの時期は?ベストなタイミングと成功のポイント
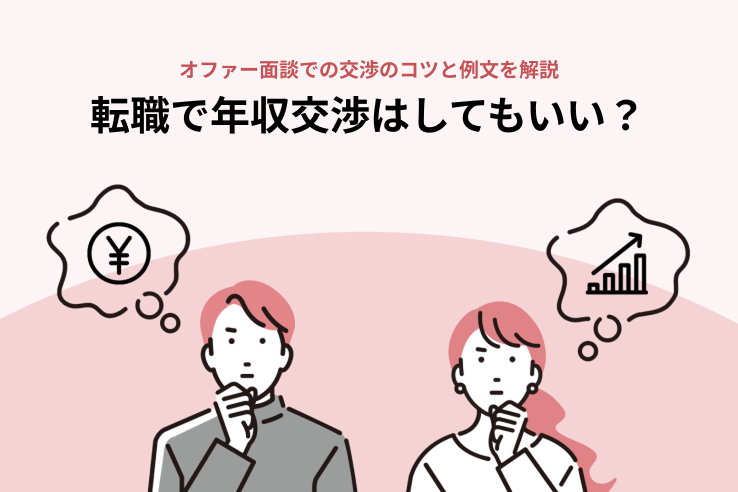
転職で年収交渉はしてもいい?オファー面談での交渉のコツと例文を解説

転職が「怖い」「不安」と感じる原因と解消法
年収800万円以上、年収アップ率61.7%
仕事のやりがいは何ですか?
今の仕事で満足な点と変えたい点はありますか?
あなたにとってのワークライフバランスとは?
パソナキャリアはあなたのキャリアを相談できるパートナーです。キャリアカウンセリングを通じてご経験・ご希望に応じた最適な求人情報をご案内します。